1分紹介動画(Youtube・音声つき)

空中庭園「補陀洛(ふだらく)」

聖福寺の麓から長い石階段を登って山上に着くと、目の前に開放的な庭が広がります。少し極楽に近づいたような、さながら空中庭園です。
この聖福寺本堂前庭「補陀洛」は、山と海を表現した枯山水です。それはちょうど和歌山の風景と重なります。遊歩道の向こうの岸は補陀洛、ご本尊の観音様のおわす浄土になぞらえられます。
しばし体と呼吸と心を調え佇んでいると、気づかされることがあります。
古くには、遙か西にある「西方浄土」を目指して紀南の沖から船でこぎ出した歴史もあります。しかし、白隠禅師はこう示されています。
「当処すなわち蓮華国、この身即ち仏なり」。
「当処すなわち蓮華国」、極楽浄土ははるか遠くにあるのではなかったのです。極楽は亡くなってから向かう場所ではなかったのです。今、自分が立っているここがすなわち極楽であり、そのまっただ中に私たちはいるんだ。その真実に気づかされます。
そして、「この身即ち仏なり」、この身がそのまま仏であるからには、自らが日々仏の振るまいをしてゆかなければなりません。この世界をそのまま極楽浄土にしてゆくために自分には何ができるか。仏(=目覚めた者)としてどのように生きてゆけばよいのか。
空中庭園「補陀洛」は、見るものに常に問いかけています。
名勝「徳雲庭(とくうんてい)」

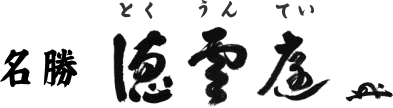
「徳雲庭」は、仏道の究極として尊ばれている次の句に由来します。
徳雲の閑古錐、幾たびか妙峰頂を下り、
他の聖人を雇って、雪を担って共に井を埋む
「徳雲」はお坊さんの名前で、徳雲尊者のことです。「閑古錐(かんこすい)」は使い込んで先が丸くなった錐(きり)で、尊者の枯れきった高い老境地をあらわします。
その老尊者が、来る日も来る日も自分の住む妙峰山(みょうぶせん)を下っては他の人々と共に雪を担いで古井戸を埋めようとする、というのです。
雪をいくら古井戸の中に入れても、井戸が埋まるわけではありません。全くの無駄事とも言えます。
同様に、どんなに修業をつんで悟りを開いても、この世に生きている限り、迷える心を持つ人々の苦しみ、悲しみがすべて消えてなくなることはありえません。
しかし、それでもなお、人々と手をとってこの世を修していくというのです。人々が苦しい時は共に苦しみます。楽しい時は共に楽しみます。
自分自身は悟りを開いて安心を得ているにもかかわらず、あえて迷える心を持つ人々のもとに降りたって、この世を生きる人々が生死の苦しみからときはなたれることを願い、やがて力尽きるその日まで苦楽を共にするのです。止むことなき菩薩の慈悲行といえましょう。
その徳雲尊者の住む場所が、この庭であるというのです。地理的にも高台にあるところから、松尾山を妙峰山に見立て、この山を訪れた人々は皆、徳雲尊者となって、人々のもとに帰っていくのです。
すべての人々が救われるその日まで、この庭は徳雲尊者の修行道場となるのでありましょう。







